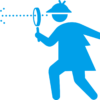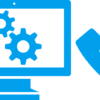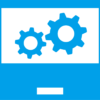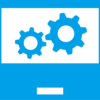Windows 10 21H2の展開予定
Windows 10の更新管理で日々御苦労されているであろう、社内SEのみなさん。
Windows 11の話題が跳梁跋扈するブログ界隈ですが、そんな話題の陰でWindows 10 21H2の展開に関する情報がMicrosoftより公開されました。
まだ日本語の抄訳は現時点で見つかっていないので上のURLは英文ですが、少しばかりの解説に社内SEとしての目線を織り交ぜながらお送りします。
今回のWindows 10 21H2の特徴は下記のとおりです。
- 更新プログラムは月例更新プロセスのように配信される
- 2021年後半に配信する予定
- Windows 10 Home, Proは18カ月のサポート、Enterprise, Educationは30カ月のサポート
- Windows 10 LTSCは展開にはまだ時間がかかるが5年のサポート予定
- Insiderプログラム登録者はBetaチャネルからRelease Previewチャネルに変更したユーザーへ配信予定
- 更新内容は主にセキュリティ関係
これらの特徴を踏まえて社内SE的目線で確認していきましょう。
展開時期とサポート期限

社内SEにとって非常に重要なのはここになります。
この展開時期がいつになるのかを踏まえておかないと社内への影響に備えることができません。
公開情報によれば2021年の後半(すでに7月なんすけど。。。)とあるので、明確に『X月Y日に配信開始!』とまではまだ決まっていないようです。
一方でInsiderプログラムのBetaチャネルからRelease Previewチャネルへ移動したユーザーに21H2を配信予定とのことです。
こちらについてInsiderプログラムを確認したところ、まだ21H2の展開は始まっていないようです。
そういう意味では、これからInsiderへの展開を実施してから問題点を確認して、さらにその後にユーザー向けとなります。
そのため、実際にはユーザーへ1カ月以内に展開ということはなく、これまでのWindows 10と同じように9月~10月ごろに配信になるのではないでしょうか。
サポート期限は既に記載の通りHome, Proは18カ月です。
管理PCの台数が数十台以上の社内SEさんはWSUSとかサードパーティー製品を利用してWindows Updateの制御をされているでしょうから、改めて更新したいPC,更新したくないPCが正しく設定されているかご確認ください。
更新内容
更新内容がセキュリティ関連とは言いましたが、具体的には下記の内容です。
- 無線WiFiセキュリティの通信規格であるWPA3 H2Eの対応
- Windows Hello for Businessがより簡単に展開できるようになる
- Windows Subsystem for Linux(WSL)やAzure IoT Edge for Linux on Windows(EFLOW)がGPU演算に対応する
WPA3 H2Eの対応

そもそもWPAというのはWi-Fi Protected Accessの略称でWiFiに接続するときの認証や暗号化の種類の内の1つです。
WPA無印、WPA2と広く利用されていましたがいずれも脆弱性が見つかったために新しい規格として『WPA3』が作られています。
新しい規格が作られても使えるようにOSが対応する方が遅くなることが多いので、今回の21H2で対応となる運びです。
社内SEとしては各社のセキュリティ方針やルールによりますが、おそらく『WPA2での通信は今後一切禁止にしてWPA3のみとします』という会社さんはいないでしょうから、特に影響はないのではと思います。
ちなみにWPA2に脆弱性があるとは言っても深刻な脆弱性ではありませんので、焦る必要はありません。
強いていえば、無線通信機能を変更することで既存の動作に影響が起きて不具合が発生、みたいなパターンはあるかもしれませんが、それほど大きな不具合はInsiderプログラムで気付かれるでしょう。
Windows Hello for Businessがより簡単に展開できる
正直、こちらに関してはよくわかりません。
グループポリシーとか使ってWindows Hello for Businessが簡単に展開出来たりするのでしょうか?
社内SE的には様子見です。
Windows Subsystem for Linux(WSL)やAzure IoT Edge for Linux on Windows(EFLOW)がGPU演算に対応する
長い見出しですが、おそらく社内ITを管理する社内SEとして影響は無いと思います。
そもそもWSLはWindows上でLinuxを動かす方法で、これを使えばPythonのコンパイルをLinuxサーバを別に立てずにUbuntuで実行できたりします。
しかしながら、ほとんど開発者向け機能なので社内SEとしてどうこう、ということは無いでしょう。
Linuxを使って機械学習を高性能GPUでやりたい、けど別でサーバーは立てたくない とか 今WSLとかEFLOWを使ってて処理速度が遅いと悩んでる みたいな人がいたら21H2でGPU演算に対応することを伝えると喜ぶかもしれません。
更新データのサイズ

社内SEの悩みのタネが更新データのサイズです。
モバイルルータでWindows Updateが容量をギガクラスで通信されて泣いた方も多いのではと思います。
今回の21H2の更新データサイズについて現時点で公開情報はありませんが、これまでの更新内容を参考にすると比較的低サイズではないかと。
月例更新のように更新されるらしいので、『特に意識していないけどいつの間にか更新されていた』という最高のパターンかもしれません。
更新にかかる時間

こちらも社内SEとして大きな悩みである更新にかかる時間です。
社内SE目線で具体化すると『Windows Updateが動くことでユーザーがWindowsで仕事をできない時間』です。
Windows 10リリース後のバージョン(1709の頃)は数GBもあるデータをダウンロードして数時間以上、更新の時間がかかるという酷いこともありました。
今回の21H2についてはまだ更新時間の実測値は分かりませんので何とも言えませんが、ここ最近のWindows Updateは改善が進んでいると思います(個人見解)。
このことを踏まえると、まさしく月例更新のように『終業時の電源オフで更新が実行され、次の日の始業時に数十分で完了』ということになるのではと希望を持っています。
まとめ
総括すると、社内SEとしての影響は限定的ではと予想します。
当然、業務利用しているソフトウェアが21H2で動くのか、動作がサポートされているのかは事前確認がいつも通り必要です。
ですが、その確認さえ取れてしまえば展開は容易と思います。